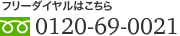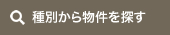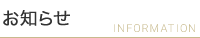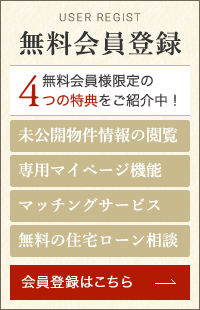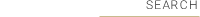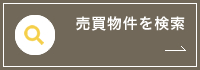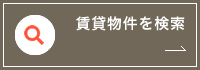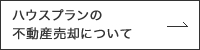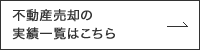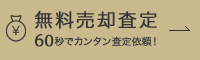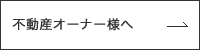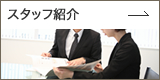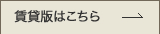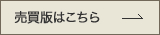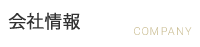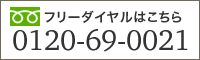相続した土地にかかる税金と評価の基本
土地を相続すると、まず気になるのが「どれくらい税金がかかるのか」という点です。相続した土地には、相続税や登録免許税、固定資産税など複数の税金が関わってきます。これらの税金は、土地の評価額や相続人の人数、土地の利用状況などによって大きく変わるため、正しい知識と準備が不可欠です。
この記事では、2025年最新の情報をもとに、相続土地の税金や評価方法、節税対策についてわかりやすく解説します。
土地の相続税評価額の決まり方
土地の相続税評価額は、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法で決まります。
路線価方式は、土地が面している道路ごとに国税庁が定める「路線価」を基準に、土地の面積を掛けて評価額を算出します。たとえば、路線価が1㎡あたり10万円で、土地が200㎡の場合、相続税評価額は2,000万円となります。
一方、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価する「倍率方式」が用いられます。倍率が1.1で固定資産税評価額が1,000万円なら、相続税評価額は1,100万円となります。
さらに、土地の形状や広さ、立地条件によって評価額が加算・補正されることもあります。例えば、角地や二方道路に接している土地は評価額が加算されますが、間口が狭い、奥行きが長い、不整形地である場合は評価額が減額される補正が適用されます。
こうした補正は専門的で細かな条件が多いため、個人で判断するのは難しいことが多いです。実際の評価額は、固定資産税の課税明細書や国税庁の路線価図、倍率表などで確認できます。
相続税の基礎控除と課税対象額
相続税が課されるかどうかは、相続財産の合計額と基礎控除額のバランスで決まります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。たとえば、相続人が2人の場合は4,200万円までが非課税となります。
土地の評価額や預貯金、株式などすべての相続財産の合計が基礎控除額を超える場合、その超えた部分に対して相続税がかかります。土地の評価方法によっては、思いのほか課税対象額が大きくなることもあるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
なお、2025年は団塊世代の高齢化による「2025年問題」が注目されています。これにより相続税申告の件数が増加し、申告や納税の手続きがより重要になると予想されています。
相続税の節税対策|小規模宅地等の特例
相続税の負担を大幅に軽減できるのが「小規模宅地等の特例」です。これは、被相続人が居住または事業に使っていた土地について、一定面積までの評価額を最大80%減額できる制度です。
たとえば、自宅の敷地として使われていた土地(330㎡まで)は、相続人が引き続き住む場合などの要件を満たせば、評価額が8割減となります。これにより、相続税が大きく軽減されるケースも多く見られます。
ただし、特例の適用には細かな要件があり、例えば相続人が一定期間その土地に住み続ける必要があるなど、注意が必要です。要件を満たさない場合は特例が受けられなくなるため、申告前に必ず専門家に確認しましょう。
土地の相続にかかるその他の税金
土地を相続した際には、相続税だけでなく、他にもさまざまな税金や費用が発生します。代表的なものが「登録免許税」と「固定資産税」です。
登録免許税
登録免許税は、土地の名義変更(相続登記)を行う際に必要な税金です。税額は「固定資産税評価額の0.4%」で計算されます。例えば、評価額が2,000万円の場合、登録免許税は8万円となります。相続登記にはこのほかにも必要書類の取得費用などの実費がかかります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地所有者に課される地方税です。相続によって土地を取得した場合、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。遺産分割協議が終わっていなくても、法定相続人全員が納税義務者となることもあります。
固定資産税の評価額は市町村が決定し、3年に一度評価替えが行われます。納税通知書は毎年5月ごろに届きますので、内容をよく確認しましょう。
相続登記の義務化とその影響
2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続によって土地を取得した場合、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。これを怠ると過料が科される可能性があるため、早めの手続きが大切です。
相続登記を行うことで、名義が明確になり、将来的な売却や活用がスムーズに進められるようになります。相続登記には登録免許税がかかりますが、相続手続きの第一歩として必ず行いましょう。
土地を相続した後の活用と売却について
土地を相続したものの、利用予定がなかったり、管理が難しい場合は、売却や賃貸、駐車場経営などの活用方法を検討するのも選択肢の一つです。特に、空き地や空き家のまま放置しておくと、固定資産税の負担だけでなく、管理責任や近隣トラブルのリスクも増えます。
売却を検討する場合は、まず不動産会社に査定を依頼し、土地の評価額や市場動向を確認しましょう。売却益が出た場合には譲渡所得税がかかることもありますが、相続から3年以内に売却すれば特別控除が適用される場合もあります。
例えば、相続した土地を早めに売却することで、相続税の納税資金に充てることができるほか、将来の管理負担や税金リスクを軽減できます。
2025年の相続土地税制の最新動向
2025年は、相続税の路線価が全国的に上昇傾向にあることや、相続登記の義務化など、相続土地に関する税制や手続きが大きく変化しています。
また、今後は人口減少や空き家問題の深刻化に伴い、土地の相続や売却に関するルールや税制がさらに見直される可能性もあります。
最新の路線価や評価倍率は国税庁のホームページで公開されており、毎年確認することが大切です。
相続税や各種特例の適用条件も細かく変わることがあるため、最新情報を常にチェックし、必要に応じて専門家に相談しましょう。
まとめ
土地の相続には、相続税・登録免許税・固定資産税など複数の税金が関わります。評価額の算出方法や特例の活用、相続登記の義務化など、2025年の最新ルールをしっかり押さえておくことが、余計な負担やトラブルを避けるポイントです。
センチュリー21ハウスプランでは、土地の相続や売却、税金対策までトータルでサポートしています。相続した土地の活用や売却、税金に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続土地の売却や税金対策は、センチュリー21ハウスプランにお任せください!
(2025年7月5日作成)
※本コラムは作成日時点の情報をもとにご案内しています。法改正や自治体ごとの運用により内容が異なる場合があります。最新情報やご不明点はお気軽にお問い合わせください。